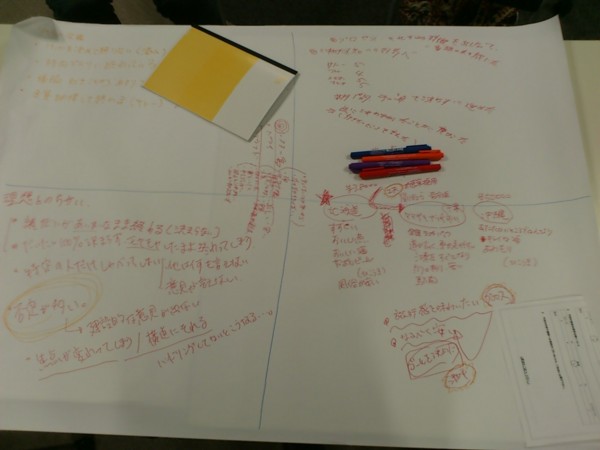『第24回すくすくスクラム 〜ファシリテーション入門だ!〜』に参加してきた #suc3rum
前回第23回から約2ヶ月、『ファシリテーション』にテーマを絞って行われた"すくすくスクラム"に参加してきました。
場所は前回同様、株式会社ECナビにて。募集上限が80名と多めだったのですが、開催告知時期が比較的ギリギリだったのもあり、30名程の参加となっていました。

講師は林栄一(TwitterID:@essence_s) さん。そして今回は仙台でも同一内容でイベントを開催、中継連携して行うという珍しい試みも実施。なかなか面白いやり取りとなってました。
以下メモ。
- Introduction to facilitation
- View more presentations from eiichi hayashi
- ファシリテーターとは
- あんまり人に認められない→『人を認める人』
- 特定の意見を主張しない→『中立な立場でプロセスをデザインし、動かす人』
- 案を出さない→『人の考えを引き出す人』
- 知識を言わない→『人の知識を引き出す人』
- 経験を話さない→『人の経験を引き出す人』
…ここで『吉田松陰スタイル』という初めて聞く単語・ファシリテーションとの繋がり。そんなのあるんかいな?と検索掛けてみたら意外と引っ掛かりました。吉田松陰は『ファシリテーション』という観点での繋がりが大きい人物だったんですね。
- ファシリテーションの効果
- 学習スピードを高める
- チームの相乗効果を発揮
- メンバーの自立性を育む
- ※メンバーの納得性が凄く高まる。
_____________
優|成功確率 |成功確率 |
|(小) |(最大) |
(戦略の |______|______|
優劣性) |失敗 |成功確率 |
劣| |(大) |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
小 (メンバーの納得性) 大
- 同意型チーム(俺についてこい!)の特徴
- 短期決戦では高パフォーマンスを生む
- 長引くに従ってパフォーマンスは段々落ちて行く
- 補完型チーム(ファシリテーション型)
- 中長期的に成長する戦略型チーム
- 補完チームのシナジー曲線は段々上がっていく
- ファシリテーションの4つの行動
- 場をデザインする
- チーム設計
- プロセス設計
- アイスブレイク
- 引き出す
- 傾聴と質問
- 非言語メッセージ
- 非攻撃的自己主張
- 構造化する
- 論理コミュニケーション
- 図を使うコミュニケーション
- 合意を形成する次への学びを作る
- 意志決定手法
- コンフリクトマネジメント
- 場をデザインする
- ファシリテーターの役割
- 内容はチームに任せ、プロセスの舵取りだけを行う。
- 中立な立場で支援。
- 手を出しすぎない。
- 考える機会を奪わない。
- 見えない所で頑張る。
- メタレベルの認知(一歩引いて俯瞰)
- 議論内容ではなくて、すすみかた、発散度、収束度、参加者の参加度、権威勾配(エライひととそうでない人の差)・・・少ない方が良い。強いとヤバイ(隠蔽される)。
- 内容はチームに任せ、プロセスの舵取りだけを行う。
- ファシリテーションの場
- 平等で公平
- 人と意見を切りはなす
- チームが自分たちで考えて、自分たちが決めたと感じること
- メンバーが尊重されている体験があること
- チームが学ぶ機会であること
- プロジェクトの成功とは?
- 決められたタイミングで、顧客(市場)要望にマッチした品質で商品を提供すること。
- ・・・本当にそれだけ?
- メンバーの成長する
- 人のスキルやモチベーションは管理出来ない・・・プロジェクト達成の犠牲になった人は?
- プロジェクトは有限
- チームは次のプロジェクトに取り組む
- ファシリテーションとは
- グループの力を最大限引き出す
- 物事をよういにする触媒
- 本来すすむべき方向に進むことを助ける
- 進む力を妨げる要因を回避する
- チームメンバーがそのままで、チームに貢献出来ることを実感する
- メンバー一人一人の自発性意識を高め、衆知を集め、意志決定を促進する
- チームメンバー自ら成長しようとする
- 現実に行われている会議と理想との違い?
-
- ★ワークショップ★
- 良好のプランを立てる
- 各自の行きたいところを考える
- 反対の方法で最終的な結果を決める
- 各自の行きたいところを発表し、話しあいによってグループの行き先を決める
- 行き先が決まったら
- どのようなプロセスで決まったかを書き出す
- 決め手になったことは何かを書き出す
- 全員の満足度を確認する
- うまく行かなかった点を書き出す
- 良好のプランを立てる
- ★ワークショップ★
- ファシリテーションの4つの行動:詳解
- ■場をデザインする
- 場を温める
- 目的やゴールを共有する
- ルールを決める
- プロセスをその時その場に合わせて設計する
- 効果的なチームを作る
- アイスブレーク
- 緊張を解きほぐす
- メンバーが肯定的にリラックス
- 簡単なゲーム
- ■場をデザインする
-
-
- プロセスデザイン
- 発散終息型
- 問題解決型
- 林さんの使ってる汎用フレームワーク
- プロセスデザイン
-
1.場を設定する →目的、ゴールを明確にする 2.状況を把握する、データを収集する 3.取り組むべき課題を取り出す 4.アイデアをどんどん出す →なるべく沢山。常識外れのでも可。(多くの人は常識を外してアイデアを出す、って事をあんましない) 5.アイデアをグルーピングして構造化する 6.現実的なプランにまとめる 7.5W1H 8.1〜7を振り返り 9.メンバーを力づける
-
-
- 場をデザインする>ディスカッションサイズ
- 議論の状況によってグループのサイズを調整
- 1.いろんなネタを沢山あつめたいとき
- 2.意見があまりでないとき
- 恥ずかしくて言えない場合
- 言いにくい意見がある場合
- 個人的な感情に基づく対象であるとき
- 3.特定の人からしか意見が出ないとき
- 4.全体で意見を共有したいとき
- 場をデザインする>ディスカッションサイズ
-
-
- ■引き出す
- 聴く
- 傾聴:アクティブリスニング
- ペーシング(相手のペースに合わせる)
- 受け取る
- 復唱
- 心で聴く
- 訊く
- 観る
- 応える
- 聴く
- ■引き出す
-
-
- 質問のリズム
- 1.広げて情報を収集
- 2.閉じて明確化
- 3.拡げてtが遺作の可能性をひろげる
- 4.閉じて対策を具体化
-
-
-
- 非言語メッセージをとらえる
- 場の空気を読む
- ゼスチャー
- 非言語メッセージをとらえる
-
-
-
- 要約して他のメンバーに分かりやすいように言い換える
- 事例と比喩を使って、直感的に理解させる
- 質問を使って自己主張する、等々
-
-
- 『人vs人』から『問題vs私達x』の構図に変えて対応。
-
- ■構造化する
- 主張を正しく理解させる
- ポイントと位置付けを明らかにする
- 議論を構造化する
- 論理が繋がるように再構築をする
- ■構造化する
-
-
- 図示の4つの基本形
- ツリー構造
- サークル構造
- フロー構造
- マトリクス構造
- 図示の4つの基本形
-
-
-
- ファシリテーション・グラフィック…練習で向上出来る!
-

ファシリテーション・グラフィック―議論を「見える化」する技法 (ファシリテーション・スキルズ)
- 作者: 堀公俊,加藤彰
- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
- 発売日: 2006/09/01
- メディア: 単行本
- 購入: 22人 クリック: 124回
- この商品を含むブログ (117件) を見る
-
-
-
- 紙に書く事でファシリテートして行く。
-
-
-
- ■合意形成
- メリットデメリット
- 多数決
- コンセンサス法
- ■合意形成
-
- ★ワークショップ2★
- 旅行のプラン2テーマは同じ。前回の内容を踏まえて再演。
- 安易で多数決で妥協せず、全員が満足する行き先を決める
- 相手を攻撃せずに、協調的なコミュニケーションを心掛ける
- お互いの主張を良く聞き、主張の裏にある本質的な欲求を話し合う
- 旅行のプラン2テーマは同じ。前回の内容を踏まえて再演。
- ★ワークショップ2★
-
-
- 行き先が決まったら
- どのようなプロセスで決まったかを書き出す
- 決め手になった事は何かを書き出す
- 決めるために工夫したことを書き出す
- 行き先が決まったら
-
- 今日の振り返り/フィードバック…学びを次に。
- 気付きを与える
- 気付きをわかちあう
- 意味を考えさせる
- 学びを一般化する
- 応用を考えさせる
- 実行を促す
仙台と東京では同じスライド資料を用いてファシリテーションの講義・実践を行っていたのですが音声の調整度合い等もあり時折こちら(東京)の講義と仙台の講義のタイミングが合わない場面も。こっちの講義中に仙台で笑い声が聞こえた際に講師の林さん自ら『うるせ〜!』と発言する場面も(笑)初めての試みなのでこの辺は御愛嬌、と言った所でしょうか。同時開催というのは面白い試みなのでまた機会があればやってみて欲しいですね。
セッションを終えてからの振り返りでは、仙台・東京それぞれがワークショップでの振りかえりをまとめつつ報告し合いました。
また、ワークショップ自身ですが講義が駆け足気味、かつ慣れない進め方と制限時間の短さで理想的なファシリテーションっぷり、会議進行とは行かなかったですね〜。(^^;) 個人的に/グループとしても慣れない部分もあったとは思いますが…こういう所で『ファシリテーター』な人が円滑に場を進められると良いのだろうなぁとは実感。
講師の林さんによるとこれらのワークショップは本来はもっと時間を掛けて行うもののようで、それらを2時間にぎゅっと濃縮した形で講義されていたんですね。駆け足感があったのも納得。

資料自体も相当数のページボリューム、非常に読み応えのある内容となっています。後日UPを期待したい所ですね。そしてもっとじっくり、踏み込んだ形で『ファシリテーション』の実践も行ってみたいな〜と思いました。
講師の林さんは、来たる2011/09/03(土)に開催される『XP祭り2011』でもワークショップを実施されるようです。興味のある方はこちらのイベントにも足を運んでみてはいかがでしょうか。